地方自治法が施行されてから60周年を記念した硬貨
大浦天主堂は長崎市にあるカトリックの教会です。幕末の開国直後に建てられた、この教会は日本におけるキリスト教徒の復活の象徴でもあります。
戦国時代、長崎の港は日本で唯一ヨーロッパ各国とのつながりを持つ港でした。そして、続々とキリスト教の宣教師たちが日本での布教を目的に来航したことから、長崎を中心にキリスト教が浸透していくことになります。特に九州では各地に教会や修道院が建てられ、大名までもがキリスト教に改宗したことで爆発的に広まっていきました。
しかし、順風満帆に見えた布教活動も豊臣秀吉が全国統一を果たしたことで陰りが見え始めます。1587年に発布された宣教師の国外退去を命じたバテレン追放令にはじまり、1596年にも日本二十六聖人と呼ばれる宣教師や信徒26人の処刑が長崎で行われました。江戸時代に入った1612年にキリスト教禁教令が発布されると、教徒への弾圧はより苛烈になり、各地のキリスト教徒は開国まで隠れて過ごすこととなります。
幕末、日本が開国すると、さすがの幕府も神戸や長崎などの外国人居留地に限ってはキリスト教を認めます。そのなかで大浦天主堂には、250年の江戸幕府の支配下のなか、信仰を守り続けていた日本のキリスト教徒たちが続々と訪れ、長崎一帯に数多くの信徒がいたことが明らかになりました。
地方自治法施行60周年記念貨幣(長崎県) 1000円銀貨幣
1865年の開国間もないころに建てられた大浦天主堂は、日本国内に現存するキリスト教建築物としては最古の建物です。正式名称を日本二十六聖殉教者聖堂といい、名前のとおり1596年に長崎の地で処刑された26人の宣教師と信徒に対して捧げられた教会です。ゴシック様式で建てられたレンガ造りの教会は、洋風建築としてははじめて国宝に指定されました。
また、そばに添えられた椿は長崎県の県花です。その花言葉は「誇り」。迫害と闘い続けてきたキリスト教が根付く長崎ならではのデザインといえるでしょう。
| 発行年 | 平成27 |
|---|
| 図柄(表) | 大浦天主堂と椿 |
|---|
| 図柄(裏) | 雪月花 |
|---|
| 素材 | 銀 |
|---|
| 品位 | 純銀 |
|---|
| 量目 | 31.1グラム |
|---|
| 直径 | 40mm |
|---|
地方自治法施行60周年記念貨幣(長崎県) 1000円銀貨幣買取価格
地方自治法施行60周年記念貨幣(長崎県) 500円バイカラー・クラッド貨幣
ゴシック様式の教会である大浦天主堂には、ほかの国の教会同様にステンドグラスが使われています。特に、正面大祭壇奥にある「十字架のキリスト」を表したステンドグラスは、大浦天主堂のシンボルです。
創建当初はフランスのマン市にあるカルメル会修道院から寄贈されたものが用いられていましたが、原爆や台風の被害などで多くのステンドグラスが壊れています。そのたび遠い異国の地で布教を続けた宣教師、そして信仰に殉じた信徒たちを称えた聖堂を守るべく修復が続けられています。
| 発行年 | 平成27 |
|---|
| 図柄(表) | 大浦天主堂とステンドグラス |
|---|
| 図柄(裏) | 古銭のイメージ |
|---|
| 素材 | ニッケル黄銅、白銅及び銅 |
|---|
| 品位(千分中) | 銅750、亜鉛125、ニッケル125 |
|---|
| 量目 | 7.1グラム |
|---|
| 直径 | 26.5mm |
|---|
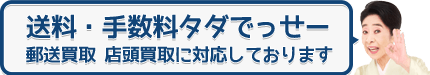 送料・手数料無料 すべて0円!宅配買取、店頭買取に対応
送料・手数料無料 すべて0円!宅配買取、店頭買取に対応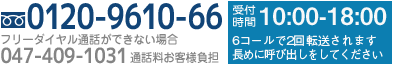 フリーダイヤル0120-9610-66
フリーダイヤル0120-9610-66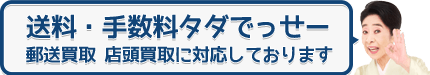 送料・手数料無料 すべて0円!宅配買取、店頭買取に対応
送料・手数料無料 すべて0円!宅配買取、店頭買取に対応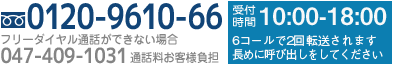 フリーダイヤル0120-9610-66
フリーダイヤル0120-9610-66