一円銀貨の種類や買取相場は?本物と偽物を見分けるポイントも解説!

一円銀貨は1870年(明治3年)から1914年(大正3年)の間に鋳造された銀貨です。
従来、貿易用貨幣として製造・発行されましたが、1878年(明治11年)以降より国内でも流通するようになりました。
そんな一円銀貨は、種類や状態によって希少価値が大きく変わってきます。この記事では一円銀貨の種類や買取相場、本物と偽物を見分けるポイントについて解説します。
一円銀貨の種類
一円銀貨は発行した年代によってデザインや大きさに違いがあります。それぞれの銀貨の特徴について、順番に見ていきましょう。
旧一円銀貨
| 鋳造時期 |
1870年(明治3年) |
| 直径(mm) |
38.58 |
| 質量(g) |
26.96 |
| 品位 |
sv900 |
旧一円銀貨(きゅういちえんぎんか)は、1870年(明治3年)に発行された銀貨です。
表面には、中心に円を描くような龍の絵柄と、発行年数や金額を表す文字。裏面には、中心に太陽の模様と、それを囲むように桐と菊の葉が描かれています。
この銀貨は約2年しか発行されていないことから希少価値が高く、数万円程度で取り引きされています。
新一円銀貨
| 鋳造時期 |
1874年(明治7年)~1914年(大正3年) |
| 直径(mm) |
1887年以前:38.6/1887年以降:38.1 |
| 質量(g) |
26.96 |
| 品位 |
sv900 |
新一円銀貨(しんいちえんぎんか)は、1874年(明治7年)から発行が停止される1914年(大正3年)まで発行された銀貨です。
この銀貨は発行された年代によって大きさに違いがあり、1887年以降につくられた一円銀貨はそれ以前のものよりも0.5mmほど直径が小さいです。
また、大型から小型への切り替え時である1874年は、大型と小型の両方が存在します。
デザインは大型も小型も共通で、表面には中心に円を描くような龍の絵柄と、発行年数や『大日本』という文字。裏面には、金額を表す『一圓』や菊紋の刻印があります。
買取相場は大型銀貨の方が高く、1万円から。小型は数千円程度が相場となります。
貿易銀
| 鋳造時期 |
1875年(明治8年)~1877年(明治10年) |
| 直径(mm) |
38.58 |
| 質量(g) |
27.22 |
| 品位 |
sv900 |
貿易銀は諸外国との貿易専用に発行された大型銀貨です。
裏面に『貿易銀』と表記されているのが大きな特徴ですが、その他に表面の縁に『420 GRAINS.TRADE DOLLAR.900 FINE』という文字が刻印されているという特徴もあります。
貿易銀は品位の高い外国の貨幣に対抗する目的で、従来よりも品質を向上させてつくられました。しかし期待した結果が得られなかったため、約3年で製造が停止されたと言われています。
そのため希少性が高く、10万円以上の高価買取も期待できます。
本物なのに価値が大幅ダウン!?荘印や修正品とは?

一円銀貨は、主に中国や台湾などの対外貿易用として使用されました。
中国の両替商には受け取った貨幣に自社の荘印(極印)を打つ習慣があり、表面に荘印が打たれた一円銀貨や貿易銀が多数存在しています。
また、このような荘印入りのコインに対し、後で上から銀を流して印を埋めたものを『修正品』と呼びます。
写真の赤い丸で囲んだところをよく見てみると、色がおかしかったり模様が潰れていたりするのがわかるでしょうか。
これらの銀貨は本物であることに違いはないのですが、コレクターとしてはやはり手を加えられていない綺麗な状態の物を集めたいもの……。
こうした事情から、荘印や修正品の収集品としての価値は大幅に下がります。
丸に『銀』と打たれた1円銀貨はレア!?

一方、印が打たれていることで価値を持つ一円銀貨も存在します。
丸に『銀』の文字の刻印は、外国の両替商がつけた荘印とは異なり、日本の造幣局によって正式につけられたものです。
丸銀打ちの銀貨が流通した経緯について、簡単に解説します。
1878年(明治11年)から、日本国内でも一円銀貨が流通しはじめました。
しかし、1897年(明治30年)に日本政府は金本位制を採用するために貨幣法を制定。その際に一円銀貨の流通を停止し、引換を禁止することを決定します。
ところが日清戦争後、台湾や朝鮮では一円銀貨が広く流通しており、すぐにその通用を禁止することができませんでした。
そのため、しばらくの間、丸に『銀』の極印を押して外地(主に朝鮮や台湾)でのみ通用することを認めたのです。
しかし、この措置は市場の混乱を招き、1年も経たずに中止されました。
このような経緯から丸銀の刻印が入った一円銀貨は希少性が高く、コレクターの間で高値で取り引きされています。
一円銀貨の真贋の見分け方
一円銀貨の中には、本物に似せた模造品(いわゆる偽物)も存在します。一円銀貨の真贋を見分けるポイントは主に以下の3つです。
順番に解説していきます。
重さ
一円銀貨の真贋を見分ける最も簡単な方法は、重さを量ることです。一円銀貨に限らず、金貨や銀貨は品位(金と銀の割合)が決まっているため、重さが一定となるためです。
一般的な一円銀貨の重さは26.9gです。ここから+-1.0g以内であれば本物と判断できます。逆に重さが+-1.0g以上違う場合は、ほぼ模造品と判断してよいでしょう。
絵柄
絵柄をよく見ることでも本物と模造品を見分けることができます。
ポイントは『線の凹凸がはっきりしているか』『細かな模様が再現されているか』『線や模様が均等であるか』の3つ。

上の写真は旧一円銀貨の本物と模造品を並べたものです。
龍のデザインを確認してみると、本物は細かな線まで鮮明に刻印されているのに対し、模造品は彫りが細かな模様まで再現できていないのが一目瞭然ですね。
また、周りを囲む小さな丸い点もよく見ると均等でないことがわかります。

こちらは新一円銀貨の本物と模造品の写真です。模造品は線が均等でなかったり、目が粗かったりする部分があります。また、色味も本来の銀の色と比べると違和感があります。
エッジ

銀貨のエッジ(銀貨のふち、側面)を見てみることも重要です。本物は目が細かく均等であるのに対し、模造品は目が不均等であったり潰れていたり、バリが目立つ傾向があります。
本物と模造品のエッジの違いについては明治金貨のコラムでも解説しています。
貴重なコインほど偽物に注意!
希少性が高いコインほど偽物に注意しなければなりません。特に明治7年や8年などの特年(発行枚数や流通量の少ない年号)や貿易銀は、非常に多くの偽物が出回っています。
中には重さや品位も合わせてつくられた『スーパーコピー』と呼ばれる、かなり精巧な偽物も存在しています。
こうした模造品であっても、側面(エッジ)のつくりの違いを注意深く観察すれば本物と比べて違和感があることに気づきますが、そう簡単に判断がつくものではありません。
お持ちの一円銀貨の価値を知りたい方は、金貨や銀貨の買取実績のある専門店で査定を依頼することをおすすめします。
金貨買取本舗でも無料で査定を受け付けています。まずは『メール』『LINE』『お電話』からぜひお問い合わせください。
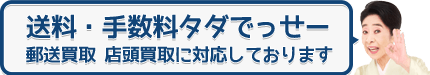 送料・手数料無料 すべて0円!宅配買取、店頭買取に対応
送料・手数料無料 すべて0円!宅配買取、店頭買取に対応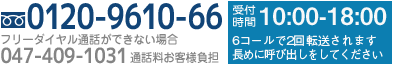 フリーダイヤル0120-9610-66
フリーダイヤル0120-9610-66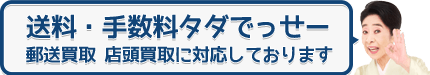 送料・手数料無料 すべて0円!宅配買取、店頭買取に対応
送料・手数料無料 すべて0円!宅配買取、店頭買取に対応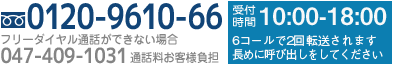 フリーダイヤル0120-9610-66
フリーダイヤル0120-9610-66