旭日竜小型五十銭銀貨(あさひりゅうこがたごじゅっせんぎんか)は1871年(明治4年)に鋳造された銀貨です。表には金額を示す『五十銭』の文字と、中心には円を描くような竜が彫られています。
同じ旭日竜小型五十銭銀貨でも、竜の特徴が異なる『大竜』と『小竜』の2種類にわけられています。両方とも大きさはほとんど同じですが、大竜のほうが2mmほど大きいつくりです。
お持ちの旭日竜小型五十銭銀貨の買取価格を知りたい方は『無料査定のお申し込み』『LINEで査定』やお電話から是非お問い合わせください。
旭日竜小型五十銭銀貨の種類と価格
旭日竜小型五十銭銀貨が鋳造されていた時期には、旭日竜大型五十銭銀貨もつくられていました。
どちらも表と裏のデザインはほとんど変わりませんが、大きさで見分けることが可能です。また旭日竜大型五十銭銀貨は鋳造年数が長いですが、旭日竜小型五十銭銀貨のほうが鋳造枚数が多いです。
しかし旭日竜小型五十銭銀貨の『大竜』は品質が一番低いものでも、旭日竜大型五十銭銀貨の2倍の価格で取引されることもあります。
一方旭日竜小型五十銭銀貨の小竜は、旭日竜大型五十銭銀貨と価値はほとんど変わりません。
以下が種類一覧となります。
旭日竜小型五十銭銀貨 大竜(だいりゅう)

旭日竜小型五十銭銀貨大竜は小竜と見分ける際に、表面の竜を見比べるとわかりやすいでしょう。
表面の明治の文字のそばに描かれている、二又の炎のような模様(大火炎)を見てください。大火炎の外側のトゲが2つだと大竜です。
しかし大火炎で見分けることができるのは前述の一ヵ所のみなので、ほかの大火炎を見て判断しないよう気をつけましょう。
旭日竜小型五十銭銀貨 小竜(しょうりゅう)
旭日竜小型五十銭銀貨小竜は、大竜と同じ大火炎の部分のトゲが3本です。それ以外の竜のデザインや書体は大竜とほとんど同じです。
大竜と小竜を見分けるには大火炎を確認するしかありませんが、ほかの古銭に比べると違いがわかりやすいので、誰でも簡単に見分けることが可能です。
旭日竜小型五十銭銀貨小竜は一つの大火炎にトゲが3本ということもあり、2本の大竜よりトゲ同士の間隔が狭いです。
それ以外の大火炎はトゲが等間隔に並んでいるため、1枚だけで判別するなら小竜のほうが簡単に見分けられるでしょう。
しかしかなり品質が良い状態の小竜でも、大竜のほうが価格が高く、約7倍も価格に差がつくこともあるため、プレミアがつきにくい銀貨です。
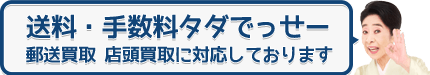 送料・手数料無料 すべて0円!宅配買取、店頭買取に対応
送料・手数料無料 すべて0円!宅配買取、店頭買取に対応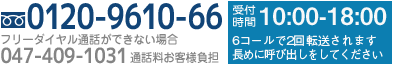 フリーダイヤル0120-9610-66
フリーダイヤル0120-9610-66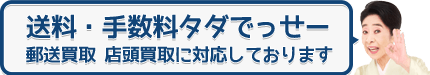 送料・手数料無料 すべて0円!宅配買取、店頭買取に対応
送料・手数料無料 すべて0円!宅配買取、店頭買取に対応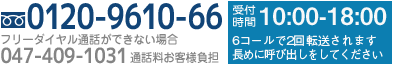 フリーダイヤル0120-9610-66
フリーダイヤル0120-9610-66