天保一分銀(てんぽういちぶぎん)は天保8年(1837年)から安政元年(1854年)につくられた銀貨です。
天保から明治にかけて複数の一分銀がつくられてきました。なかでも天保一分銀は初期の一分銀なので『古一分銀』とも呼ばれています。
表面と裏面の桜の刻印で、一つだけ斜めになっている『逆桜』という特徴があります。逆桜の位置や、有無により価格が変わります。
また天保一分銀は側面に3つの小さな桜の刻印も施されています。これは天保一分銀だけの特徴です。
お持ちの天保一分銀の買取価格を知りたい方は『無料査定のお申し込み』『LINEで査定』やお電話から是非お問い合わせください。
逆桜とは?
ほとんどの一分銀には、必ず一ヵ所『逆桜(ぎゃくざくら)』と呼ばれる特殊な刻印があります。しかし同じ時代につくられた一分銀でも逆桜の位置が異なるものもあります。
逆桜とは銀貨の枠に彫られた桜の刻印の向きが、ほかの桜と逆さに彫られている状態のことです。規則正しい桜の並びのなかに、ひとつだけ傾いたように見えるので簡単に見分けられます。
しかしまれに両面に逆桜がないレアな一分銀も存在します。この一分銀はコレクターからの需要が高く、同じ特徴の一分銀でも、両面逆桜なしのほうが高価で取引されています。
天保一分銀の種類と価格
天保一分銀は両面に逆桜のない種類が見つかっている一分銀です。その価格は100,000円もすることもあります。
本記事では文字の特徴が普通品と異なる3種を紹介します。高い種類は普通品の約28倍も高値で取引されることもあります。
以下が種類一覧となりますが、記載している価格は状態が非常に良い場合での参考買取価格になります。その点ご留意ください。
天保一分銀 跳分(てんぽういちぶぎん はねぶん)
跳分とは、表面の『分』の字の一画目が上に跳ねている状態を指します。チェックマークのような見た目なので、古銭に詳しくなくても比較的判別しやすいでしょう。
以降に挙げている『長柱座』や『長跳分』よりも価格は低いですが、普通品より高価のケースが多いです。同じ跳分でも裏面の文字の特徴の違いで価格も変わります。
そのため表面の跳分だけでなく裏面もよく確認することをおすすめします。
天保一分銀 長柱座(てんぽういちぶぎん ちょうちゅうざ)
長柱座とは、裏面の『座』の土の縦線が文字の一番上まで伸びている状態を指します。口と人の字を突き抜けるような勢いは、長柱座だけの特徴なので、こちらも比較的わかりやすい特徴といえるでしょう。
非常に状態が良いものだと135,000円になることもあり、両面逆桜なしの天保一分銀よりも高額になることもあります。
天保一分銀 長跳分(てんぽういちぶぎん ちょうはねぶん)
長跳分とは跳分よりも長く『分』の字の一画目が跳ねている状態のことです。跳分よりも、跳ねた部分がさらに上に伸びているので、跳分との区別はつきやすいでしょう。
しかし長跳分は非常に希少な種類なので、見つけることができたらラッキーです。状態が良いものは220,000円の価値がつくこともあり、このことから長跳分は両面逆桜なしの天保一分銀よりも珍しいことがわかります。
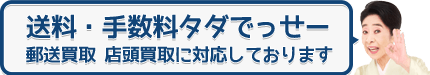 送料・手数料無料 すべて0円!宅配買取、店頭買取に対応
送料・手数料無料 すべて0円!宅配買取、店頭買取に対応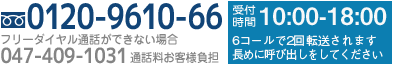 フリーダイヤル0120-9610-66
フリーダイヤル0120-9610-66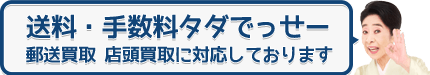 送料・手数料無料 すべて0円!宅配買取、店頭買取に対応
送料・手数料無料 すべて0円!宅配買取、店頭買取に対応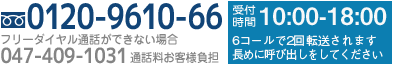 フリーダイヤル0120-9610-66
フリーダイヤル0120-9610-66