享保小判(きょうほうこばん)は正徳4年(1714年)~元文元年(1736年)に発行された小判です。
名前に享保とありますが、正徳の時代につくられているため『正徳後期小判』とも呼ばれています。
当時は慶長時代に発行された慶長小判以降の小判の純度が、時代の進みとともに下がる現象が起きていました。諸説ありますが、日本の金の採掘量が減ったことが原因といわれています。
純度が低い小判は金の価値を基準とした流通において、大変価値が低いものとみなされていました。
そんななか享保小判は国内の物価高を解消する目的で、純度が高くなるようにつくられました。結果、日本でつくられた小判のなかで『最も純度の高い小判』となりました。
表面は畳に似た細かな横線が等間隔に引かれています。裏面は左下に職人の名前が彫られています。
付加価値の高い小判の買取価格は市場価格や在庫状況によって変化する為、最新の価格については『無料査定のお申し込み』や『お電話(0120-9610-66/受付時間10:00~18:00)』からお問い合わせください。
プレミア価値を持つ『大吉』とは?
当時、判金はひとつずつ手作りだったので、完成時には職人がサインを刻印していました。作成した職人の親方と、作成した職人本人の名前を一文字ずつ、小判裏面の左下に刻印します。
親方→職人と地位の高い順に名前を彫るこの習わしですが、親方のサインが『大』、職人のサインが『吉』となることがあります。二つあわせて『大吉』と読めるため、当時から縁起が良いと人気でした。
この刻印には現代でも高い価値が認められており、大吉の有無だけで同じ小判でも価格がかなり異なります。
偶然大吉と献上大吉の見分け方
偶然大吉と献上大吉、どちらも『大吉』のサインがありますが、見分けることができます。献上用目的で丁寧につくられた献上大吉は、外枠の触感がなめらかできれいな仕上がりです。
一方、偶然大吉は流通目的の金貨の刻印が、思いがけず大吉になった金貨のため、献上大吉よりも外枠がきれいではありません。
さらに大吉の文字自体も献上大吉のほうがしっかりと打ってあるため、一見して大吉とすぐにわかる外枠がきれいな金貨は、献上大吉の可能性が高いでしょう。
享保小判の種類と価格
享保小判のなかには偶然大吉や、佐渡で鋳造された佐渡小判といったプレミア価値が高い種類も存在します。
さらにそれらのなかでもレアな、裏面に『弘』や『久』の刻印が入った享保小判もあります。
しかし弘や久の刻印つきは市場に出回ることがほとんどなく、記録などで存在が確認されているだけに留まります。
もし上記の刻印をもつ享保小判を見つけることができたなら、偶然大吉以上の価値がつく可能性が高いです。
希少性などのプレミアは、ほかの小判と比較して低いですが、金地金で計算するよりも、小判としての価値のほうがはるかに高いです。
遭遇しやすいぶん、多くの枚数を売ることで高い利益につなげやすいです。また見た目や重さが慶長小判と非常に似ています。
両者の小判は価格が異なるので、自分で価格を調べたい場合は以下の詳細な特徴も確認してみてください。
以下が種類一覧となりますが、記載している価格は状態が非常に良い場合での参考買取価格になります。その点ご留意ください。
享保小判 偶然大吉(きょうほうこばん ぐうぜんだいきち)
偶然大吉とは、裏面の左下にある職人のサインが『大』と『吉』でそろっている、大変縁起の良い小判のことです。
献上用にはじめから大吉で打たれたものと違い、流通用の中で偶然生まれた大吉の享保小判は非常に珍しく価値も高いです。
しかしながら同じ純度やそれ以下の純度の小判の大吉より、プレミア価格はわずかに低いです。
それでも多少傷がある状態でも80万円の値がついたケースもあるため、すぐに安値と判断して手放してしまうともったいないです。
大吉表記が享保小判よりもプレミアがつくぶん高いため、裏面もしっかり確認しましょう。
享保小判の買取実績(実例)

2025年1月に『御徒町店』にて享保小判をお買取りしました。上記画像がお買取りした小判の写真です。
享保小判は、慶長小判と外観が似ているものの、『光次』の書体に特徴があります。
具体的には、『光』の六画目の払いと、『次』の四画目が重ならずに離れていることが特徴で、これにより享保小判と判断いたしました。
享保小判は、金の含有量が86.1%(K20)と、江戸時代に作られた小判の中で最も金の含有量が高いものです。
そのため、金としての素材価値だけでも、2025年1月31日時点の金相場で約23万円の価値があります。
さらに、査定には享保小判ならではのプレミア価値も加味されます。
今回の小判には、裏面に刻印されている『弘』や『久』『偶然大吉』など、特に希少価値の高い刻印はありませんでしたので、通常の享保小判として鑑定いたしました。
なお、今回の享保小判には貨幣鑑定書が付属しておりませんでしたが、古銭をお持ち込みいただく際に鑑定書があると、買取がスムーズに進むだけでなく、本物であることを証明する重要な資料としても役立ちます。
貨幣鑑定書は、日本貨幣商協同組合が発行し、見識のある鑑定委員によって真贋が確認された際に発行されます。
鑑定書がない場合、買取が難しくなることもありますので、可能であれば鑑定書も一緒にお持ち込みいただくことをお勧めします。
これらの要素を総合的に考慮し、最終的に36万円でお買取りさせていただきました。
なお、こちらの買取価格はあくまで参考価格となります。金の相場の変動や、小判に付属するアイテムの有無などによって、買取価格は大きく変動することがございます。
最新の価格については『無料査定のお申し込み』や『お電話(0120-9610-66/受付時間10:00~18:00)』からお問い合わせください。
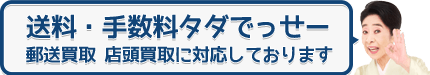 送料・手数料無料 すべて0円!宅配買取、店頭買取に対応
送料・手数料無料 すべて0円!宅配買取、店頭買取に対応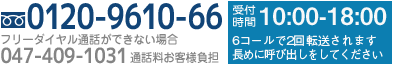 フリーダイヤル0120-9610-66
フリーダイヤル0120-9610-66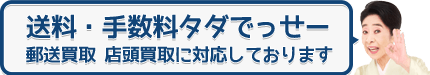 送料・手数料無料 すべて0円!宅配買取、店頭買取に対応
送料・手数料無料 すべて0円!宅配買取、店頭買取に対応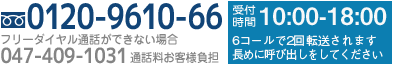 フリーダイヤル0120-9610-66
フリーダイヤル0120-9610-66