正徳小判(しょうとくこばん)は正徳4年(1714年)につくられた小判で、鋳造期間は1年と非常に短く、希少性が高いです。
また正徳小判は純度が高い慶長小判の再現を目的につくられたため、純度が高いことも特徴の一つです。
この小判は『武蔵小判』とも呼ばれていました。
由来は慶長小判の原型である武蔵墨書小判からきており、慶長小判と似た特徴の小判であったことが別名からもうかがえます。
表面は全体的に畳のような模様が彫られており、中央には小判鋳造の代表者である『光次』のサインが刻印されています。
また裏面にも印鑑のような丸い枠の中に、光次の文字が彫られています。小判のほとんどはつくられた時代を表す文字が刻印されていますが、正徳小判には時代印はありません。
付加価値の高い小判の買取価格は市場価格や在庫状況によって変化する為、最新の価格については『無料査定のお申し込み』や『お電話(0120-9610-66/受付時間10:00~18:00)』からお問い合わせください。
プレミア価値を持つ『大吉』とは?
当時、判金はひとつずつ手作りだったので、完成時には職人がサインを刻印していました。作成した職人の親方と、作成した職人本人の名前を一文字ずつ、小判裏面の左下に刻印します。
親方→職人と地位の高い順に名前を彫るこの習わしですが、親方のサインが『大』、職人のサインが『吉』となることがあります。二つあわせて『大吉』と読めるため、当時から縁起が良いと人気でした。
この刻印には現代でも高い価値が認められており、大吉の有無だけで同じ小判でも価格がかなり異なります。
偶然大吉と献上大吉の見分け方
偶然大吉と献上大吉、どちらも『大吉』のサインがありますが、見分けることができます。献上用目的で丁寧につくられた献上大吉は、外枠の触感がなめらかできれいな仕上がりです。
一方、偶然大吉は流通目的の金貨の刻印が、思いがけず大吉になった金貨のため、献上大吉よりも外枠がきれいではありません。
さらに大吉の文字自体も献上大吉のほうがしっかりと打ってあるため、一見して大吉とすぐにわかる外枠がきれいな金貨は、献上大吉の可能性が高いでしょう。
正徳小判の種類と価格
正徳小判は正確には1714年の5月~8月までしかつくられていません。期間は記録上のものですが、現存数の少なさから記録はかなり正確といえるでしょう。
その希少性からコレクターの人気も高く、高額なプレミアがつきやすいです。
しかし慶長小判と同じ小判をつくることを目的としていたため、宝永小判と慶長小判は見分けることがとても難しいです。
この2種類の小判はそれぞれ価格が異なるので、きちんとした価格を把握したい場合は、細かな特徴を把握しておきましょう。
また鋳造期間が少なくプレミア価格が高い正徳小判は偽物も存在します。ほかの小判と区別するだけでなく、金メッキなどの偽物でないかも確認しましょう。
以下が種類一覧となりますが、記載している価格は状態が非常に良い場合での参考買取価格になります。その点ご留意ください。
正徳小判(しょうとくこばん)
正徳小判には裏面の刻印が偶然大吉になったものが存在します。しかし市場に出回ることは非常に珍しく、記録上の存在であるともいえます。
また鋳造期間が短いため献上判がつくられていたかも定かではありません。いずれにしても裏面の左下に『大吉』と彫られているなら、かなりの高額が期待できます。
正徳小判と慶長小判を見分けるためには、表面の『光次』の刻印を確認してください。正徳小判は光の6画目が、下の次の字と重なり、一筆書きのような書体です。
慶長小判や享保小判など、正徳小判とデザインが似ている小判は、『光』と『次』の文字がはっきりとわかれているので、判断しやすいといえます。
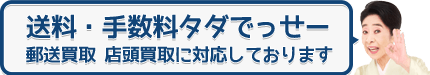 送料・手数料無料 すべて0円!宅配買取、店頭買取に対応
送料・手数料無料 すべて0円!宅配買取、店頭買取に対応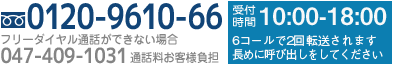 フリーダイヤル0120-9610-66
フリーダイヤル0120-9610-66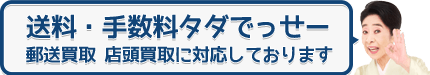 送料・手数料無料 すべて0円!宅配買取、店頭買取に対応
送料・手数料無料 すべて0円!宅配買取、店頭買取に対応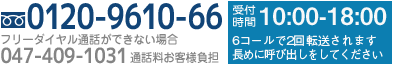 フリーダイヤル0120-9610-66
フリーダイヤル0120-9610-66